はじめに: 数学的構造の眼で舞台を観る
20世紀最高のオペラ歌手マリア・カラスが現役引退後に行った伝説のマスタークラスを題材にした舞台『マスタークラス』。
2025年に再演された日本版(森新太郎演出)では、元宝塚歌劇団トップスターの望海風斗が、かつてのようには歌えなくなった後年のカラスを演じています。
【 #マスタークラス 】#望海風斗 主演『マスタークラス』
本日19時開幕🎉濃密な稽古を重ねた作品がいよいよ初日を迎えます💚
20世紀最高峰の歌姫と謳われた #マリア・カラス の「公開授業」をぜひ #世田谷パブリックシアター に"受講"しにいらしてください‼️
— ワタナベ演劇公式 (@watanabe_engeki) March 14, 2025
私自身、この舞台を観劇しながら、深い感銘を受けました。
傑作。これは望海風斗の代表作になると思う。虚実の間でカラスのディーヴァをユーモラスに演じながら、混濁する回想で観客を一点に集中させる。薄皮を剥くように辿り着いた先の喪失。彼女自身が一流の歌手だからこそ生成する説得力がある。自在に変幻する生声の表現に聴き惚れた。#マスタークラス pic.twitter.com/SrDVx4wYxM
— ヤシオユアン (@YasioE) March 20, 2025
そして、一見遠い存在に思える圏論という数学の概念が、この作品の構造を鮮やかに浮かび上がらせることに気付きました。
このレビューでは、舞台上の「理想」と「現実」という二つの世界を圏に見立て、それらを結ぶ射・関手・自然変換のメタファーで作品構造を紐解いてみます。
圏論とは
皆さんは、ほぼ圏論について聞いたことがないと思いますので、あらかじめ簡潔に説明しておきます。
圏論とは、ある種の数学的な「世界の見方」です。
圏論では、主に対象と、それらの間を結ぶ射(矢印)からなる構造(圏)を扱います。
これは演劇でいえば、「対象」は劇中に登場する人物や場所、出来事、概念などに相当し、「射」はそれらの間に生じる相互作用、つまり人物同士の関係性や感情の伝達、物語の進展や場面転換などにあたります。
圏とは、まさにこれらの要素(人物や状況)が互いに結びついてできる、ひとつの劇的世界そのものだと言えるでしょう。
さらに圏論では、一つの圏から別の圏への構造的な写像を関手と呼び、異なる関手同士をつなぐ変換を自然変換と呼びます。
なるべく簡単に言い換えると、関手は「ものの見方」を定め、自然変換は「見方同士をつなぐ」ものと考えるとイメージしやすいでしょう (第2回 圏論の三つの根本概念 「圏」「関手」「自然変換」 | gihyo.jp)。
なお、このレビューでは、数学の厳密さよりも構造の美しさを前面に、観劇体験に基づく発見的な視点を展開していきます。
理想圏と現実圏: 物語を貫く二項構造
『マスタークラス』の物語には、大きく二つの「世界」が並行して存在しているように見えます。
一つはカラスが体現する伝説的芸術の世界=理想、もう一つは生徒たちや教室の状況に即した現実です。圏論の言葉を借りれば、これらはそれぞれ「理想圏」と「現実圏」として捉えられるでしょう。
理想圏には、オペラ芸術の高みや過去の輝かしい記憶(カラス自身の栄光、劇中で歌われるアリアが持つドラマ)があり、現実圏には、目の前の舞台上で展開する肉体的・日常的な諸要素(歌うことに必死な若い生徒たちや、ステージ上の些細な出来事)が含まれます。
マリア・カラス(望海風斗)は、まさにこの二つの圏を行き来する関手のような存在です。
彼女は自身の人生経験と芸術観(理想圏の要素)を、生徒たちの歌唱指導(現実圏での出来事)に投影しようとします。例えば、生徒ソフィーに対して、音符ではなく“痛みの一刺し”を求めなさいと諭す場面では、単なる音程以上に感情を重視する彼女の芸術理念(理想)が、生徒の歌唱という現実の行為に対応付けられています。
カラスの指導そのものが、現実圏の出来事を理想圏の価値観へと対応付ける関手的な役割を果たしているのです。
しかし、理想と現実は常にすんなりとかみ合うわけではありません。むしろ、そのずれこそがドラマを生んでいます。ここで圏論的な自然変換の視点が有用です。
カラス(教師)と各生徒(学習者)は、それぞれオペラという芸術を解釈する異なる視点=関手を持っていると言えます。
カラスの視点は「自分の苛烈な人生経験を通して芸術に命を吹き込む」というものであり、一方、生徒たちの視点は未熟ながらも純粋に音楽に向き合おうとするものかもしれません。それら二つの関手が出会う場がマスタークラスという場面であり、理想圏から現実圏への橋渡しをする試みが行われます。ここで教師の助言や叱責は、まさに両者の「見方をつなぐ」自然変換の役割を果たします。
うまく自然変換が作用すれば、生徒の解釈はカラスの高みに近づき、両者の理解が調和する(図式が可換になる)でしょう。逆に言えば、その変換が不自然であったり、ねじれたりすれば、理想と現実は噛み合わず不協和音を生むことになります。
舞台全体を通して感じられるのは、カラスが必死に追求する「芸術の真実」(理想圏のエッセンス)と、生徒たちが直面する「自分の未熟さや恐れ」(現実圏の課題)の対比です。
カラスは生徒に対し「もっと感じて。感じて。感じ尽くして歌いなさい」と繰り返し要求します。それは、生徒の現実に理想の基準を流し込み、彼ら自身の中に眠る感情資源を引き出そうとする行為です。
観客である我々は、カラスが舞台上で度々遠い目をして過去の栄光に思いを馳せる姿も目撃します(理想圏へのトリップ)。一方で、その最中にも照明の変化や周囲の反応で現実の教室に引き戻される(現実圏への回帰)という構造が繰り返されます。
この往還運動そのものが、舞台の構造的美しさであり、関手と自然変換のメタファーで捉えると極めてエレガントなのです。
オペラ・アリアと内面変容の圏論的図式
『マスタークラス』では3人の生徒が登場し、それぞれ有名なオペラ・アリアに挑戦します。それぞれの場面が、一種の圏論的図式として読み解けるのも興味深い点です。各生徒(対象)がアリアを歌うという行為(射)を通して、内面的な変容(射の結果)が生まれます。その過程を、理想圏(オペラの役柄の感情世界)と現実圏(生徒本人の心情)の相互作用として詳述してみましょう。
ソフィー(ベッリーニ『夢遊病の女』のアリア)
最初の生徒ソフィーは、緊張に震える若いソプラノです。
彼女が選んだアリアは、ベッリーニ作曲『夢遊病の女』から、ヒロインのアミーナが愛を失った嘆きを歌う難曲でした。
これは失恋の痛みという強い感情が核にある曲ですが、当然ながら若いソフィー自身はまだそのような深い心の傷を経験していません。ここでカラスは彼女に対し、「本当にその感情がわかっているの?」と容赦なく問い質します。劇中ではソフィーに「心が折れたことがあるか?」と尋ね、経験がないソフィーに業を煮やしたカラスが「誰だって失恋くらいするものよ」と吐き捨てるように言う場面がありました(実際、カラスは自分も若い頃醜く太っていて恋愛で傷ついた過去を持っています。
このやりとりは、ソフィーという対象Xからオペラの役柄アミーナという対象Yへの感情の射を成立させようとする試みに他なりません。カラスは関手的に「ソフィーの経験」を「役柄の感情」に対応付けようとしました。
しかし対応付けるべき経験値がソフィーに欠如していたため、自然変換がうまく働かず、カラスは苛立って何度も彼女を途中で止めます。ソフィーは涙を浮かべ萎縮しますが、この涙こそ彼女の現実の心が動いた証でもあります。皮肉なことに、カラスの厳しい言葉がソフィーに初めて“喪失の痛み”を与えたとも言えるでしょう。
結果的にソフィーは深く傷つきますが、その経験自体が彼女にとって貴重な糧となったはずです。カラスの辛辣さはソフィーに芸術の厳しさを教え、彼女の内面世界に変化(射の結果)が生じました。図式的に表せば、ソフィーの現実の涙という結果がアミーナの嘆きと重なり合い、カラスという関手を通じてXからYへの射が初めて意味を持った瞬間と言えるかもしれません。
トニー(プッチーニ『トスカ』のアリア)
二人目の生徒トニーはテノール歌手で、プッチーニ『トスカ』を選びます。
彼は「偉大な歌手になって金持ちになりたい」という野心満々の青年で、登場時にはやや自己顕示的な態度すら見せます。彼が歌う曲は、第1幕でカヴァラドッシが歌うアリアです。この曲は絵描きでもある主人公が恋人トスカへの愛と美を歌う情熱的な内容ですが、トニーの最初の歌唱は表面的でカラスを満足させません。カラスは冒頭の一節で彼を止め、「帰りなさい」とまで言い放ちます。
しかしトニーは食い下がり、帰ることを拒否する。ここでカラスは態度を軟化させ、彼に曲の背景を語り始めます。「今は春の朝10時、あなた(カヴァラドッシ)は最愛のトスカと一晩中愛し合って幸せな気持ちでいる……」といった具合に情景を詳細にイメージさせるのです。
この指導法は、トニーに対して想像力という関手を働かせたと言えるでしょう。単に音程をなぞっていただけの彼の歌唱に、物語世界の情景と感情を対応付ける関手を導入したのです。カラスの言葉により、トニーの中で現実の自分と役柄カヴァラドッシが重なり始めます。結果、再開した彼の歌唱には先ほどまでとは違う情感が宿り、今度はカラスが恍惚とするほどの出来栄えを見せました。
この成功体験により、トニーの内面にも変化が起きたと推察できます。最初は名声欲ばかりが先走っていた彼が、音楽そのものの力を実感した瞬間だったのではないでしょうか。図式的には、トニー(X)からカヴァラドッシの感情世界(Y)への射が、カラスの助言という自然変換によって可換となり、音楽表現(理想圏)と本人の歌唱(現実圏)が見事に一致したと言えます。観客としても、この場面では彼の伸びやかな歌声にカラス同様心を奪われ、現実と理想の融合する快感を味わいました。
シャロン(ヴェルディ『マクベス』のアリア)
最後の生徒シャロンは二幕に登場するドラマティック・ソプラノです。
彼女は華やかなロングドレスで現れ、ヴェルディ『マクベス』よりマクベス夫人の手紙読みの場のアリアに挑みます。マクベス夫人は夫に王位簒奪をけしかけるためなら「赤ん坊さえ殺してみせる」と宣言する強烈な野心家であり、このアリアには彼女の冷酷な決意と狂おしい野望が凝縮されています。
カラスはシャロンに「何かのために殺したいと思ったことは?」と問い、彼女の中の野心や情念を引き出そうと試みました。しかしシャロンは圧倒され、舞台袖に一度引っ込んでしまいます。彼女はカラスの放つ理想のプレッシャーに耐えかねたのです。
それでも思い直して戻ってきたシャロンは再挑戦しますが、カラスは細かく注文を付け、ついには自分がマクベス夫人になりきって手紙を読み上げて見せます。しかしその歌声は悲しいほどに掠れてしまい、理想とは程遠いものでした。この時点で、シャロンの抱いていたカラスへの理想像が崩れ始めたのかもしれません。それでもなおカラスはシャロンに歌わせようとしましたが、結局は自分の往年の録音を流すという禁じ手に出てしまいます。
この一連の流れは、シャロンにとって自己喪失から自己発見への過程だったと解釈できます。憧れのマリア・カラスに否定され、一度は舞台から逃げた彼女(自己喪失)。しかしもう一度奮起して戻ってきた時、彼女の中には何か覚悟のようなものが芽生えていたでしょう。そして決定打となったのが、理想だと思っていたカラスの醜態を目の当たりにしたことです。シャロンはついに爆発し、あの衝撃的な「嫉妬」発言となりました。これはシャロンにとっての自己発見とも言えます。
すなわち、「憧れていたカラスも完全ではない。自分は自分のやり方で進むしかないのだ」という境地に達したのではないでしょうか。以降、彼女は舞台から去り物語から退場しますが、その背中は敗走というより一人の人間の決意を感じさせました。図式で表すなら、シャロン(X)からマクベス夫人の狂気(Y)への射は最後まで成立しなかったものの、代わりにシャロン(X)からカラス本人(Z)への異なる射が生じたように思えます。
すなわち、シャロンは役柄ではなくカラスという人間を「看破する」矢印を放ったのです。これは、彼女に新たな視座をもたらしました。理想圏への到達には失敗したかに見えたシャロンですが、現実圏での真実の瞬間に触れたことで、彼女自身の内面には別種の覚醒が起きたと言えるでしょう。
以上の三つのケースを比較すると、それぞれ異なるパターンの圏論的図式が見えてきます。ソフィーの場合は、欠如した経験を埋めるために現実の痛みを与えるという逆説的手段で射を成立させようとし(部分的には成功し)、トニーの場合は想像力という自然変換で関手同士を調停し射の可換性を達成、シャロンの場合は本来目指した射とは別の射が生じて既存の図式自体を描き替えてしまった、という具合です。
どのケースも、単に「生徒が上達した/失敗した」という物語上の出来事に留まらず、理想と現実の交錯という本作のテーマをそれぞれ異なる角度から示しています。圏論の概念を借りることで、その構造的違いと美しさがより一層浮き彫りになるのです。
シャロンの決裂: 自然変換のねじれと射の不可逆性
物語が最高潮に達するのは、第二幕でのソプラノ学生シャロンとカラスの劇的な対立の場面でしょう。カラスの指導に耐えかねたシャロンが涙ながらに食ってかかり、「あなたはもう歌えないくせに若い人が歌えるのを妬んでいるんでしょう!」と怒りをぶつけ、教室を飛び出してしまうシーンです。
この瞬間、舞台上の空気は張りつめ、理想(カラスへの憧れや敬意)と現実(カラスもまた衰えた一人の人間だという事実)が激突します。
圏論的に見れば、この場面は自然変換が大きくねじれた瞬間と言えます。本来、教師カラスの視点(関手)と生徒シャロンの視点(関手)を橋渡しするはずだった指導(自然変換)は、途中までは機能していました。
実際、カラスはシャロンにマクベス夫人の手紙の場面を歌わせるにあたって「何かのために殺したいと思ったことはある?男性でもキャリアでもいい」と問いただしています。これは、そのアリアで描かれる激しい野心と狂気の感情を理解させようと、シャロン自身の内面から対応する感情を引き出そうとする試みでした。
カラスの意図は明白です――マクベス夫人が持つ殺意のエネルギーを、シャロンの現実の感情に対応付け(関手的マッピング)しようとしたのです。これは本来、理想の役柄の感情と現実の自分の感情を結びつける自然変換として機能するはずのものでした。
しかし、シャロンは「そんなこと考えたこともない」と答えます。彼女はまだ若く、人生経験も浅いため、カラスの要求するような激情を理解できないのです。
カラスは「人生がいずれ教えてくれる」と返しますが、この時点ですでに両者の溝は深まっています。カラスはついにシャロンの歌唱を途中で止め、自分自身がかつてその曲を歌った1952年のライブ録音を舞台上に響かせてしまいます。これはいわば、理想圏そのものを現実圏に直接持ち込んでしまった行為です。本来なら生徒自身が到達すべき芸術的高みに、教師が自分の過去の栄光で蓋をしてしまった。この瞬間、自然変換は破綻しました。シャロンの内面で進行していたはずの変容プロセス(関手間の変換)が強制的に断ち切られ、理想と現実の対応関係はもはや保たれなくなったのです。
その結果として起きたのが、シャロンの激しい決裂です。彼女の反発は、圏論でいうところの射の不可逆性を象徴しています。師弟関係という一つの射(カラスからシャロンへの影響の矢印)は、この対立によって一度進んだが最後、元に戻すことのできない不可逆な変化をもたらしました。
シャロンはカラスに楯突くという一線を越えてしまった以上、もう以前のような素直な学生には戻れません。カラスの側もまた、自らの弱点を突かれたことで、教師としての威厳という「矢印」は折れ曲がってしまったように見えます。
この決裂の場面は観客である私たちにも痛烈な印象を残します。理想圏の住人であるかに見えたカラス=望海風斗に、現実圏の論理(老いと嫉妬の現実)で刃が突き立てられる瞬間だからです。まさに現実が理想を貫いた瞬間であり、その構造的衝撃は凄まじいものがありました。
舞台上では静寂が支配し、カラス(望海風斗)の表情には崩れ去った理想を目の当たりにした痛みと、それでもなお保とうとする矜持とが去来していたように感じられました。不可逆な射としてのシャロンの決断により、物語は大きく揺さぶられ、我々は理想と現実の乖離が生むドラマの力を目撃するのです。
「現実圏」の象徴としての道具係
この舞台には、カラス、生徒たち、伴奏者に加えて、もう一人重要な人物(といっても役名すらない存在)が登場します。
それが道具係の男性です。一見取るに足らない脇役ですが、構造的には非常に興味深い役割を果たしています。彼は劇中でほとんど台詞らしい台詞を発しませんが、カラスに頼まれて譜面台用の踏み台を持ってきたり、飲み水やクッションを運んできたりします。しかもその態度はどこか気だるく退屈そうで、芸術談義が繰り広げられている最中にも関わらず彼だけは終始無表情です。
道具係は、まさにこのマスタークラスの現実圏を体現する象徴です。カラスが音楽や感情について高尚な薫陶を垂れるたびに、彼は無言で現れて無骨な足台をコトリと置いていく。その様子は滑稽でもあり、観客の笑いを誘う瞬間でもあります。
しかしこの笑いは、単なるコメディリリーフではなく、理想と現実のギャップそのものから生まれる構造的な笑いです。舞台があまりにも理想(芸術論・感情論)に傾きすぎないように、道具係という現実の楔が打ち込まれているのです。
圏論的に言えば、道具係は現実圏における恒等射あるいは終対象のような役割かもしれません。彼は舞台上で自ら積極的に何かを変えるわけではなく、誰に対しても影響を与えません。ただそこに「存在する」ことで、他の全ての出来事に影を落としています。
例えば、カラスが情熱的に生徒を指導する場面でも、ふと横を見ると彼が所在なげに立っている。「皆さん、これは所詮劇場での一幕に過ぎませんよ」とでも言いたげなその姿は、観客にメタ的な視点すら与えます。
つまり、我々は道具係を見ることで「いま舞台上で起きていること自体も一つの現実にすぎない」という二重構造を意識させられるのです。これにより、理想圏と現実圏の対比はさらに一段深くなります。劇中劇のような効果と言ってもいいでしょう。
加えて、道具係の存在はカラスという人物の人間臭さを浮き彫りにする装置でもあります。伝説的なディーヴァであるカラスも、脚が届かないから台が欲しいとか、座る椅子にクッションが欲しいとかいう俗な要求をする。ただし彼女自身はそれを「舞台上の道具の使い方も含めて自己演出の一部」と捉えており、決して卑近な態度では頼まない。
しかし道具係はそれを淡々と処理するだけで、カラスの威厳には一切ひれ伏さない。このアンバランスさは、理想圏の住人(カラス)に現実圏のルール(誰もが平等にただの人間だという事実)が突きつけられている構図でもあります。観客は笑いながらも、その根底にある構造的メッセージを感じ取るでしょう。
つまり、「どんな芸術の高みも、現実という地平から離れては存在し得ない」ということを、道具係の姿が暗示しているのです。
宝塚的理想性と崩れゆく理想: 主演俳優に潜むパラドクス
本作における配役の妙も、構造的視点から見逃せません。主演の望海風斗という存在自体が、一種の理想の化身と言えます。宝塚歌劇団において雪組トップスターを務めた彼女は、ファンにとって夢と希望を体現する存在でした。実際、「宝塚は観る者に夢と希望を魅せる場所」であるとしばしば言われます。
望海風斗、膨大なせりふに挑戦 主演舞台「マスタークラス」初日開幕https://t.co/brMaMvONld
元宝塚歌劇団雪組トップスターの女優、望海風斗(41)が14日、東京・世田谷パブリックシアターで主演舞台「マスタークラス」の初日を迎えた。
— サンスポ (@SANSPOCOM) March 14, 2025
男役トップとして舞台に立つ望海風斗は、現実には存在しない理想の男性像を演じ、その輝きで観客を魅了してきました。そのような宝塚的理想性をまとった俳優が、本作では声を失いつつあるマリア・カラスという「崩れゆく理想」を演じている。ここに大きなパラドクスと、それゆえの構造的意味が生まれています。
望海風斗は卓越した歌唱力で知られ、宝塚退団後もミュージカル界のトップスターとして活躍しています。その彼女が、本作ではほとんど歌わずに2時間に及ぶ長台詞劇に挑戦しました。これは劇中のマリア・カラスの状況と見事に呼応しています。
カラスは過去に一世を風靡した伝説的ソプラノでしたが、劇中の設定では声が出なくなっており、自分では歌いません。つまり「本当は歌える人が歌わない」と「本当は歌えなくなった人を演じる」という二重の構図があるのです。観客は否応なくメタな視点を誘発されます。舞台上でカラスが「あの頃のようには歌えないのよ」と語るとき、それは同時に望海風斗という稀代の歌手が歌わない選択をしている現実とも二重写しになるのです。
このパラドクスは圏論的に見れば、俳優という実在の人物(現実圏)と役柄という虚構の存在(理想圏)を結ぶ関手の特異な例と言えます。
通常、俳優から役柄への関手は、俳優の持つスキルや魅力を役に投影するものです。しかし本作では望海風斗という俳優の最大の武器である「歌」を封印することで、逆に役柄の持つ欠落(声を失ったディーヴァ)を際立たせています。まるで関手が反変的に作用しているようなものです。俳優の持つ属性をそのまま対応させるのではなく、あえて反転させて対応付ける。
このような関手の使い方によって、観客は深い構造的意味を感じ取ります。それは「絶対的な理想の輝きも、時の流れにより失われうる」という無常観であり、同時に「理想を知る者だからこそ、その喪失を演じられる」という逆説的真実です。
私が観劇していて特に印象的だったのは、ラストシーンの演出です。カーテンコールにて、舞台上に巨大なマリア・カラス本人の写真が降りてきて、カラス役の望海風斗がその前で一礼するという幕切れでした。
この瞬間、現実の俳優と伝説の人物(理想)のイメージが一つの空間に重ね合わされます。望海風斗という現実の存在が、マリア・カラスという理想のアイコンと向き合い、そして重なり合う図式です。
観客としてその光景を目にしたとき、まるで理想圏と現実圏の区別が一瞬溶解し、一つの高次元の圏に融合したかのような感覚がありました。これは、本作のテーマを見事に体現した演出と言えるでしょう。
宝塚的理想性を帯びた俳優が崩れゆく理想を演じ切り、最後にその理想そのもの(カラスの写真)と対峙する――理想と現実の対話が、舞台上で具体的なイメージとして結実したのです。
望海風斗という稀有な存在を得たことで、この舞台の構造的メッセージは一層明確になったように思います。理想は美しい。しかし理想は壊れもする。その壊れゆく様すら、美しく舞台芸術に昇華できるのだと。本作は配役のレベルにおいても、圏論的な二項対立と対応付けを孕んでいたわけです。
構造の美しさに浸って
舞台『マスタークラス』(望海風斗主演)は、表面的にはマリア・カラスという伝説の人による音楽マスタークラスの再現劇ですが、その内側には複雑で豊かな構造が息づいていました。理想と現実という二項対立があらゆるレベルに埋め込まれ、それらが時に調和し、時に衝突する様は、まるで精緻に設計された数学的な図式を見るかのようです。
圏論のメタファーを用いることで、私たちはこの舞台の隠れた構造に言語を与えることができます。関手(見方)と思えば、カラスと生徒の芸術観の違いが明瞭になりますし、自然変換(つなぎ)と思えば、その違いを埋めようとする試行錯誤の尊さと難しさが感じ取れます。射の不可逆性と思えば、一度放たれた言葉や感情が関係性を不可逆に変えてしまう舞台の緊張感に納得がいくでしょう。
何より、この舞台の構造美は観客にカタルシスを与えてくれます。理想圏と現実圏の隔たりに葛藤しつつも、最後にはそれらが一つの大きな真実(芸術とは何か、生きるとは何か)に収斂していく様は、数学で難解な証明が最後に美しく収まる瞬間にも似ています。望海風斗演じるカラスが最後に観客に語りかける「自分の深い感情を探りなさい」という言葉は、そのまま我々観客へのメッセージにも聞こえました。人生で味わう喜びや悲しみ、成功や挫折――それらすべてが芸術表現の源になるという真実です。理想を追い求め現実に揉まれながらも、人はなお何かを表現しようとする。その構造そのものが美しく、尊い。
ひとりの演劇好きとして、この『マスタークラス』を圏論的視点で眺め直すことで、一層深い敬意と感動を覚えました。舞台上の一挙手一投足、発せられる一言一句が、巨大な見えざる構造の一部となって響き合っている――そんな風に感じられたのです。理想と現実、教師と生徒、過去と現在、俳優と役柄…様々な二項対立を内包しつつ、それらを超克しようともがく人間のドラマ。そこに潜む構造の美しさに思いを馳せるとき、ただ物語を追うだけではない味わいを得ることができるでしょう。
最後に付け加えるなら、このレビュー自体も一つの圏論的試みでした。すなわち、演劇という芸術作品(対象)を数学的構造(別の対象)に写像する関手的行為であり、読者の皆さんとの間に理解という自然変換が起こればと願っています。
厳密な数学ではなくとも、構造を捉える眼差しを持つことで、演劇体験はほんの少しだけ、豊かになるかもしれない――そんな思いを込めて筆を置きたいと思います。
【参考文献】
- Terrence McNally 『Master Class』プロット概要 (Master Class | Encyclopedia.com) (Master Class | Encyclopedia.com) (Master Class | Encyclopedia.com)他
- 西郷甲矢人 「圏論の三つの根本概念」 講演レポート(gihyo.jp) (第2回 圏論の三つの根本概念 「圏」「関手」「自然変換」 | gihyo.jp)
- 婦人公論 望海風斗インタビュー 前編(2024年12月23日) (望海風斗の“歌わない”挑戦「お芝居を面白いと思い始めたのは雪組時代『星逢一夜』の頃…」)
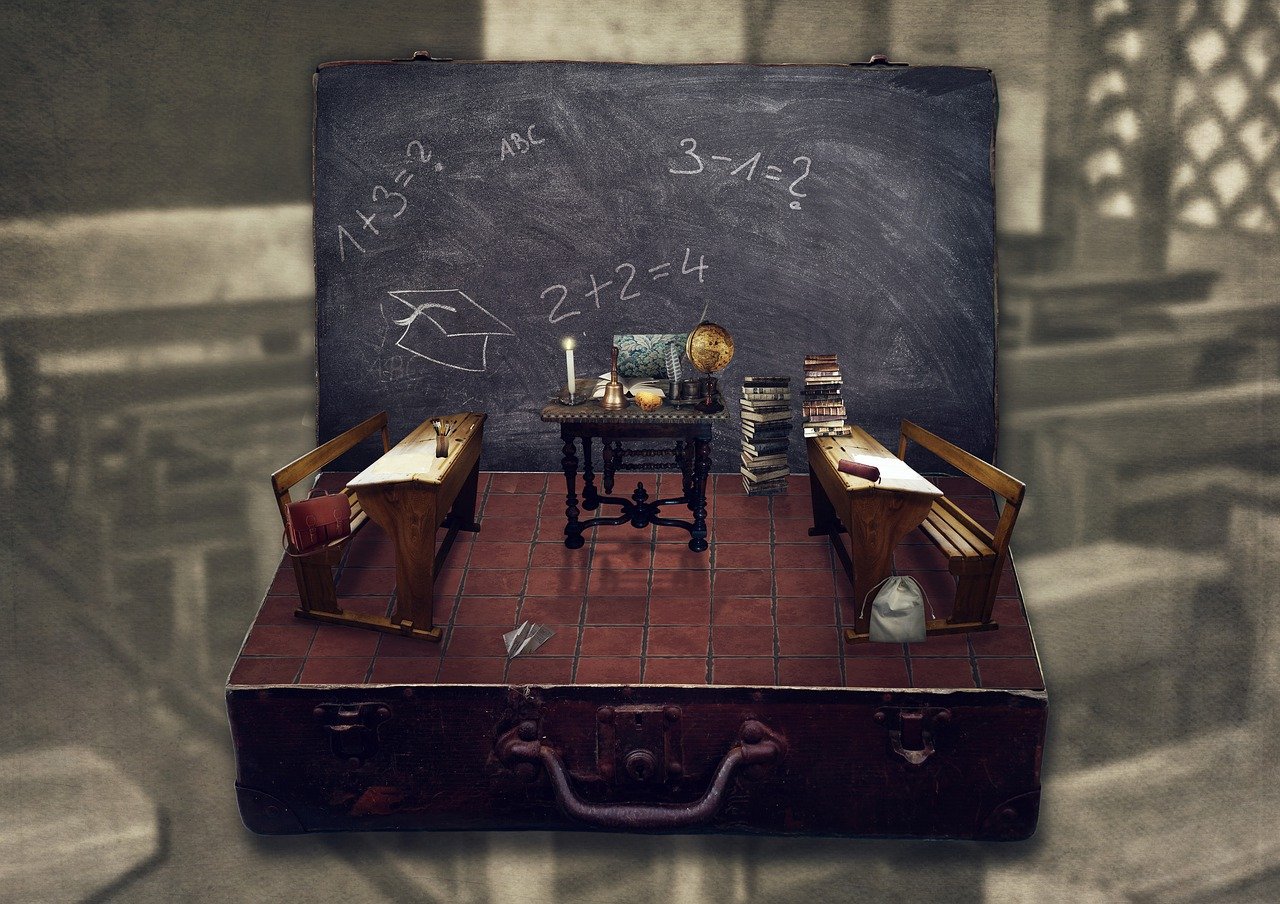











Leave a comment